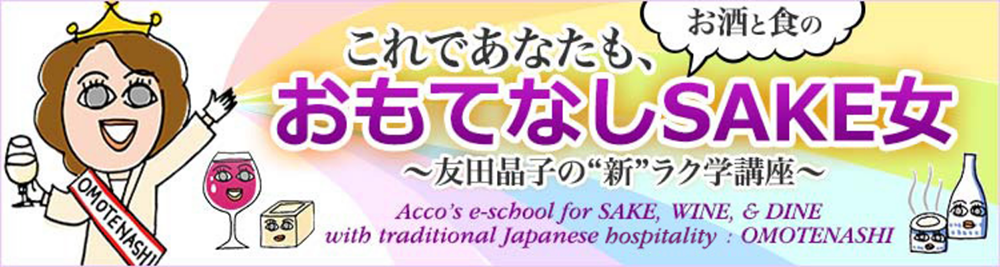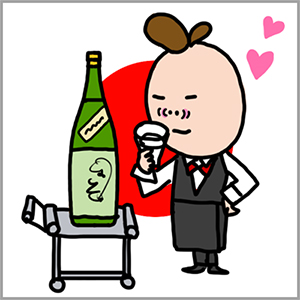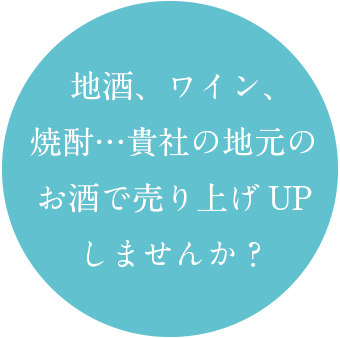日本酒のワイン的な楽しみ方。
ワイン的な楽しみ・・・・。
そうですねぇ、まずは、「ワイングラス」で飲むことでしょうか。
最近は日本酒をウィングラスで飲ませる店がちょっとづつ増えてきました。
たとえば、ワインならば、軽快な白ワインなら小ぶりなグラスで、重厚な渋味のある赤ワインなら大ぶりのグラスでなどとあるように、日本酒のタイプに合わせてグラスも変るのは楽しいものです。スッキリ軽快な日本酒ならスパークリンググラスで、濃厚な旨味の飲み応えあるタイプなら赤ワイングラスで、とか。
「温度」も重要です。ワインはタイプによってきめ細やかに適温が決められています。日本酒も幅広い温度で楽しめるお酒ですが、お酒のタイプによって微妙に温度を変えて愉しむのは実にソムリエっぽいやり方ですよね。
それからなんといっても「料理との組み合わせ」。
昔は「日本酒は何にでも合う」と言われていました。でも、日本酒にもいろんなタイプがあります。区制のない軽快なタイプやワインみたいにフルーティーなタイプ、米の旨味が凝縮した濃厚タイプに、熟成した構成はタイプなど本当にバラエティが増えてきました。でも、あっさりとした青菜のおひたしに、旨味濃厚な味わいの日本酒は野菜の優しい味を消してしまいます。個性の強い熟成酒に白身魚の薄造りでは魚の味が分からなくなります。ニンニク風味の強い焼き肉に超軽快な生酒では水を飲むのと同じこと。
そう、ここでこそソムリエの知識と経験がものを言います。
「この日本酒にはこの料理」「こちらの日本酒にはこのおつまみ」などとおすすめしてくれてこそソムリエの本領発揮というものですよね。
近い将来、世界最優秀日本酒ソムリエコンテストなどがあってもいいような気がします。すでに「世界きき酒師コンクール」は数度にわたって開催されていますが、ソムリエ業界が執り行うコンクールは難易度がさらに高くなるでしょう。
おいしく楽しく飲ませてくれるサービス技術のほかに、雄町と五百万石のブラインドテイステイスティング試験とか、酵母の違いをブラインドで当てるとか、兵庫山田錦の畑違いを当てるとか、メニューの間違い探しとか、蔵元の顔写真を見ながらどこのだれかを当てるとか・・・・、きっとそんな知識を争うのでしょうねぇ。一般消費者である飲み手にはまったく関係ないコンクール問題ではありますが、なんだか一度見てみたい気もします。